コンサルティング事業部 柳瀬 厚志 システム事業部 関藤 大樹
1. はじめに
材料における吸音性能を評価する指標の一つに「残響室法吸音率」があります。これは音が材料に対しあらゆる方向からランダムに入射する際の材料の吸音性能のことで、残響室で測定します。一般に、残響室法吸音率は材料の平均的な吸音性能を表現していると考えられており、コンサートホールなどの音響設計をはじめ、自動車内装材や建材などの吸音性能の評価値として幅広く利用されています。
今回は実験室シリーズの第5弾として、残響室法吸音率の測定における、温湿度条件による測定結果の変化とJIS A1409(1998)に記載されている補正について検討を行った結果を報告させて頂きます。
2. 残響室内の温度と相対湿度の変化
残響室法吸音率は、残響室内に試料を設置した状態(試料有り)と設置していない状態(試料無し)で残響時間を2回測定し、それらの値から算出します。しかし、測定中に室内の温湿度が変化すると測定結果も変化するので、測定者は細心の注意が必要です。なお、JISには測定中の室内の相対湿度は40%より大きいものとし、且つ測定中の温度と相対湿度は可能な限り一定にし、少なくとも表1で与えられる環境を満たすことが望ましい、と記載されています。
表1 測定中の温度・相対湿度の許容変化範囲(JIS A 1409(1998))
| 相対湿度 | 許容相対湿度変化 | 許容温度変化 | 下限温度 |
|---|---|---|---|
| 40~60% | 3% | 3℃ | 10℃ |
| > 60% | 5% | 5℃ | 10℃ |
しかし、実際には残響室の内部はもちろんのこと、外部の温湿度も適切に管理しておかなければ、残響室に人が出入りする度に温湿度は変化し測定データに影響を及ぼす可能性があります。また特に湿度は温度に比べ変化しがちでコントロールすることが難しいため、苦労されている方も多いのではないかと思います。そこで、当社では相対湿度の変化が測定結果にどの程度影響を与えるかを検証しました。
3. 相対湿度変化が測定結果に及ぼす影響(実験)
実験は当社音響研究所の小型残響室(約9m3)を使用し、加湿器を用いて室内3箇所の平均相対湿度が30~90%となるよう変化させ、その都度室内8箇所の平均残響時間を測定しました。平均残響時間の測定回数は「試料有り」時・「試料無し」時共に29回です。実施時期は秋(10月)で、温度は一定(24±1℃)となるよう管理しました。測定した試料は、一般的な多孔質繊維材料です。

写真1 実験時の残響室内の様子
まず、表1の温湿度条件を「試料有り」時の残響時間と「試料無し」時の残響時間の全て組合せ(総数=841)から吸音率を算出し、グラフに重ね描きしました(図1)。なお、グラフ中の赤線は、全結果の算術平均値を表します。
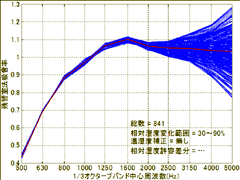
図1 温湿度条件を無視した場合
まず周波数が高いほど吸音率が大きくばらついていること分かりますが、これは「空気吸収」の影響と考えられます。一般に、高周波数帯域の音ほどそのエネルギーは空気中での伝搬中に吸収されやすく、また温湿度によってその程度が異なるので、「試料有り」時 ・「試料無し」時で温湿度が大きく変化した場合、「試料」の吸音率を適切に測定できない可能性があります。では、JISの相対湿度の下限値を守って測定すると、吸音率のばらつきはどうなるでしょうか?
実際に相対湿度が40%より大きいデータのみを使用して、再度吸音率(総数=575)を算出しました(図2)。また、さらに許容相対変化が±5%以内となる組合せで算出した吸音率(総数=119)の結果も併せて以下に示します(図3)。
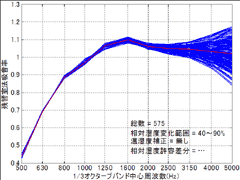
図2 相対湿度>40%&許容湿度変化= 無視の場合
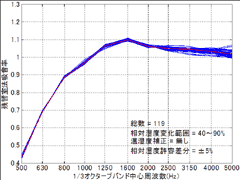
図3 相対湿度>40%&許容湿度変化=±5%の場合
図1と図2の比較より、相対湿度の下限値を守って測定すると、やはり高周波数帯域の吸音率のばらつきが小さくなることが分かります。さらに、図2と図3の比較より、少なくとも湿度変化が±5%以内となる環境で測定を行うと、ばらつきがより小さくなることが分かります。
4. 温度及び相対湿度変化の補正
JIS A 1409(1998)附属書E(参考)には、表1の許容変化範囲を超えた場合の吸音率の補正式(項)が示されています。では、この補正式を用いると吸音率のばらつきはどうなるのでしょうか?そこで、温湿度条件を無視した場合(図1)と、温湿度管理を行った場合(図3)の全結果に対し、それぞれ補正を適用してみました。結果を図4、図5 に示します。
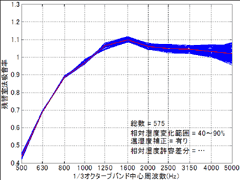
図4 温湿度条件を無視した場合(温湿度補正有り)
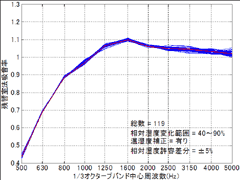
図5 温湿度管理をした場合(温湿度補正有り)
図1、図4を比較すると、温湿度条件を無視した場合、温湿度補正を行った方がばらつきは小さいことが分かります。但し、図3および図4より、温湿度補正よりも温湿度管理を行った方がばらつきは小さいので、少なくとも温湿度管理は欠かせないことが分かります。また、図3および図5より、温湿度管理を行った場合でも、温湿度補正を行った方が吸音率のばらつきは小さいことが分かります。
5. おわりに
この例からわかるように、残響室法吸音率の測定は適切な温湿度管理下で、温湿度の補正を行いつつ実施する必要があります。つまり、残響時間の測定以外にも誤差を生む要因があることを認識しておかなければならず、特に小型の残響室を導入する場合には計画時に考慮に入れておくべきポイントの一つであり、試験室の計画から計測システムまでトータルで検討できて初めて実現できます。一方、当社で残響室法吸音率の測定を行う場合は、持続可能かつ作業環境として無理のない範囲で温湿度を管理し、精度を確保しています。ご質問等ありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。




