工事部 福満 英章
まえがき
音楽スタジオにとって音響性能は大切なスタジオ機能のひとつです。 トータルな意味で、スタジオの音響性能が不十分なものであれば満足のいく録音も出来ないでしょうし、 またクオリティの高い作品に仕上げるためのトラックダウンが大変難しい作業になってしまいます。
しかし、一方ではスタジオの広さや天井高、また意匠的なデザイン等、ミュージシャンやエンジニアにとって、 居心地の良い空間作りを行うこともスタジオとして必要な大切な要素になります。
スタジオの音響設計は、限られた建築条件の枠の中で、 プロフェッショナル・ユースのスタジオとして求められる基本的な音響性能を満足させることが大前提であるわけですが、 スタジオの設計コンセプトに基づいたトータルバランスの良い空間デザインを行うための音響的なアプローチであるという認識が必要だと思います。
そして、これが個性的なスタジオの計画につながると考えています。
今回は、「スタジオ音響設計の基礎」というテーマで音響計画の基本的な考え方を述べてみたいと思います。
1. スタジオに求められる音響性能
音楽スタジオでは以下のような音響性能が必要になります。
- スタジオ作業に支障のない静けさであること。 ⇒ 暗騒音レベル
- 隣室、及び上下階に許容限度以上の音が漏れないこと。 ⇒ 遮音性能
- 作業が的確に、またスムーズに行える適度な響きであること。 ⇒ 室内音場
すなわち、各々のスタジオの規模や用途に応じた音響計画を行うわけですが、 具体的には音を遮断するための遮音計画と室内の響きを調整するための音場計画の2本立てで検討を行います。
1-1. 遮音計画
遮音計画は「音」と「振動」の両面から検討を行う必要があります。すなわち、録音が行える静かな部屋をつくるためには、 音だけではなく振動も遮断してあげなくてはなりません。地下鉄、あるいは空調機やエレベータ等の設備振動は建築の構造体を伝搬して内装材を揺らし、 室内に音として放射されます。この「固体音」と呼ばれる成分を遮断しなくてはなりません。歩行音や扉開閉時の衝撃音も同様です。 さらに、スタジオでの演奏音やコントロールルームでのモニター音のような大きな音に対しては、 ビルの躯体に入射して振動成分として構造体を伝幡し、再び音として放射される「二次固体音」の成分も無視できなくなります。 遮音された静かな空間ではS/Nが良くなりますから、小さな音でもはっきりと聞こえるようになるのです。 これは夜中に時計の音がうるさく感じられるのと同じです。(図-1参照)
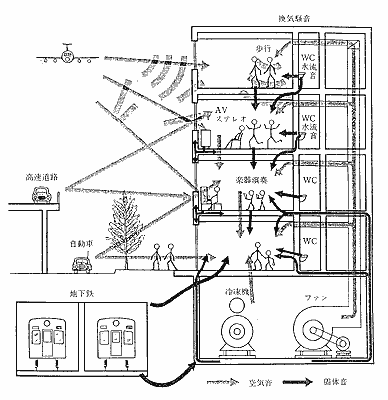
図-1 建物内外の騒音源からの音・振動の伝搬
また、通常施工される間仕切り壁(固定遮音壁)だけでは、どんなに壁を厚くしても、 先に述べた二次固体音の影響によって一定の遮音性能以上得られなくなります。これは振動の減衰が音の減衰と比べて極めて小さいことによります。 固定遮音層だけで得られる遮音性能としては 65~70dB/500Hz程度が目安となります。
すなわち、この「固体音成分」が、空調騒音等室内の音によってマスキングされて気にならない程度の大きさであれば、 音を遮音するための固定遮音層のみによる計画で良いわけですが、それ以上の静けさが必要な場合には、 固定遮音層の内側に「浮構造」と呼ばれる防振構造が必要になるわけです。(図-2参照)
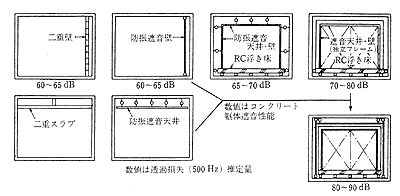
図-2 固定遮音構造と浮遮音構造
したがって、スタジオの遮音計画では、部屋の用途に応じて必要とされる静けさのレベルによって「浮構造」を採用するかどうかを決定し、 周辺騒音の大きさと目標の静けさから必要遮音量を設定して具体的な遮音構造を検討します。 なお、浮構造が必要になる静けさのレベルは、一般的には NC-25が目安になります。
一方、目標とする室内暗騒音レベルを確保するためには、建築的な遮音構造だけではなく、 空調設備の消音計画を始めとして、遮音構造を貫通する空調ダクト、電気設備、防災設備、 並びに弱電設備の配管処理を同じ遮音レベルで行う必要があります。
すなわち、遮音層貫通部の遮音処理や浮構造部分での振動絶縁処理を確実に行う必要があるのです。 特に、空調設備については、空調ガラリやダクトの管壁から侵入した音がダクト内を伝搬して隣室のガラリやダクトの管壁から透過する 「クロストーク」の影響が大きいため注意が必要です。
なお、シールド対策を行う必要がある場合は、 浮遮音層に用いるプラスターボードに銅箔貼り(厚さ 0.036mm)を行って通常は対応します。
1-2. 音場計画
室内音場の計画は、遮音構造によって得られた静かな空間を、部屋の用途に応じた適切な響きとするために、 その内側のスペースで音場仕様(吸音・反射)の検討を行います。
まず、スタジオのレイアウトを行う際に、部屋の形状が出来るだけ不整形になるように考えます。 これは、室内に平行となる面がないようにして、音響的な拡散性を高めるためです。対向する壁が完全な平行面である場合、 壁面間で音が減衰せずに行き来しますから、高音域ではフラッタリング・エコーを、低音域では定在波という音響的な障害を生じます。 したがって、必然的に少なくとも片側の壁を吸音面にせざるを得ないのです。計画場所の条件にもよりますが、 これでは音場の質を良く出来ないばかりか音場計画の自由度を狭めてしまいます。
次に、室の吸音の程度を検討します。すなわち、部屋の内装によって音のエネルギーを何%程度吸音するかを設定します。 「残響時間」は室内の響きの長さを表す物理量として良く知られていますが、その計算式は(1)式で示されます。
- Sabineの残響式
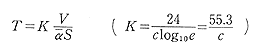
- Eyringの残響式
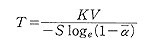 (1)式
(1)式
この式から言えることは、スタジオのレイアウトによって部屋の容積と表面積はわかりますから、 残響時間は単純に内装面の平均吸音率(α)で決定されるという点です。極端に言うと、室内のどこに吸音材を配置しようが、 その部屋で使用する吸音材の量が同じであれば残響時間は同じになるということです。 ところが、実際の音場では吸音面と反射面の位置によって音質が異なることは明白な事実ですから、 この考え方だけではスタジオの音場を設計できないことがわかります。すなわち、マイクアレンジで音が変化するように、 楽器の位置とマイク位置が大切で、この位置関係に基づいた反射面と吸音面のレイアウトが重要になります。 大まかに言えば、楽器の背面は反射面とした方が力強い音が録れるし、またミュージシャンにとっても演奏しやすい響きが得られます。
このように楽器の位置を想定した吸音面の配置を行い、低音域から高音域までバランスの良い吸音機構を工夫して、 適切な室内平均吸音率が得られるように考えるわけです。但し、波長の長い低音域の吸音処理には、 その周波数の 1/4程度の奥行きの吸音層が必要になりますから、 このスペースをどこで確保するかが室内音場と有効スペースのバランス上大切なポイントになります。
スタジオの響きの長さは録音スタイルの進歩とともに変化していますが、 一例として、現在のマルチ録音スタイルのスタジオにおける残響時間の測定結果と、 その結果から逆算して求めた室内平均吸音率の周波数特性を図-3に示します。
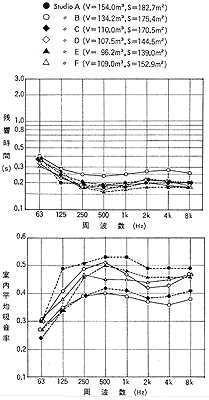 |
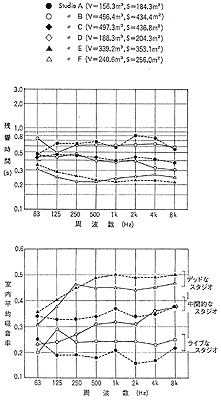 |
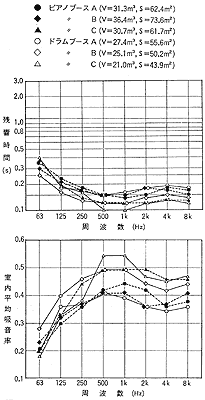 |
| コントロールルーム | スタジオ・メインフロア | ブース |
一方、コントロールルームについても同じことが言えます。コントロールルームの音源はモニタースピーカであり、 受音点はミキサーポイントになります。やはり、この位置関係を前提とした音場計画が重要なのです。
コントロールルームの音場設計の方法は、モニターシステムの進歩にともなって変化していますが、 反射面と吸音面の配置の違いによって大別すると図-4に示されるように4種類に分けられます。
| [A]ライブ・エンド デッド・エンド型 | |
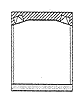 |
スピーカの背面(周囲)が反射性で、正面が吸音性のタイプ
|
| [B]デッド・エンド ライブ・エンド型 | |
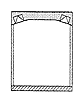 |
スピーカの背面(周囲)が吸音性で、正面が反射性のタイプ
|
| [C]分配配置型 | |
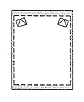 |
反射面・吸音面を交互、あるいは市松に分散させるタイプ
|
| [D] [A]+[C], [B]+[C]の中間的なタイプ | |
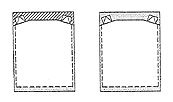 |
[A], [B]の各吸音面に反射面を追加するタイプ
|
- ライブエンド・デッドエンド型
-
無限大バッフルの考え方に基づいたスピーカ面が反射性、後壁が吸音性のタイプ。 量感はありますが、音質はソフトな傾向になります。解像度はやや落ち、音像は平面的になります。
-
- デッドエンド・ライブエンド型
-
スピーカ周辺からの有害な初期反射音をなくすためにスピーカ面を吸音性に、後壁を反射性としたタイプ。 量感は少なくなりますが音質は素直で透明感があります。定位感、解像度が良く奥行き感もあります。
-
- 分散配置型
-
反射面と吸音面を交互、あるいは市松状に配置させるタイプ。 位置による音質差は比較的少なくなりますが、音質はソフトな傾向となり、音の抜け、解像度、透明感はやや落ちます。
-
- 中間的なタイプ
-
A.、B.の吸音面に、反射面や拡散面を追加するタイプ。 音場的には各々の中間的な傾向になります。
-
しかし、どのスタイルが最良の設計方法であるということはなく、ちょうどモニターシステムを選択する場合と同じ様に、 スタジオの運営方針やエンジニアの好みによって設計スタイルを選択し、 よりクオリティの高いモニター音場となるように音響調整という手続きを通してシステムとのマッチングを図っているのが現状です。 その理由のひとつは、例えばスピーカ廻りの音響処理は音場を大きく左右するわけですが、 ハードバッフルスタイルで完全反射面を作ろうとしても、現実的には使用した材料や構造体の振動、 また背後の空間での共鳴による放射音により音は色付けされてしまいます。 一方、コムフィルターを生じる有害な初期反射音をなくすために完全吸音面を作ろうと思っても、 低音域まで十分に吸音することは現実的には無理なのです。そのため、スピーカの個性に合わせて、音響内装を調整してあげる必要が生じるのです。
また、スピーカのマウント方法も音質に大きく影響しますから、バッフル壁の中にビルトインする場合でも、 置き型、吊り型、背面固定型、ダブルエンクロージャー型等、スピーカの特徴や設置場所の条件を考慮して検討する必要があります。
2. 音響用語の解説
スタジオ計画の打合わせを行う場合、知っていた方が良いいくつかの音響用語があります。 ここではその説明を行いながら、音響設計の考え方の側面を述べてみたいと思います。
(1) dB(A)
人の耳は低音域に対して鈍感な聴感特性を持っています。この人の耳の感覚に近似した、 騒音計の「Aフィルター」を通して測定した値を dB(A)と言い、物理的な音の大きさの単位である「dB」と区別しています。
通常は、人が感じる音の大きさと理解しておいて支障ありません。
但し、人の聴感特性は音の大きさによって変わり、90dB(A)程度の大きさになると、 低音域の感度が良くなりフラットに感じれる様になるのは人の聴感特性のおもしろいところです。
(2) NC値
Noise Criteria Value の略で、室内における騒音の基準のことです。 一般的には室内騒音の大きさ、すなわちスタジオの暗騒音レベルを評価したり許容値を示すのに使われます。 騒音レベル/dB(A)では、周波数特性を規定することができませんから、人の聴感特性を逆にしたような基準曲線をもとにして、 全ての周波数帯域のレベルが下回る曲線の値をNC値としているのです。参考に、スタジオの許容NC値と測定結果の一例を図-5、図-6に示します。
| 室 名 | 無意味騒音 | 有意味騒音 | |
| NC | N | M' | |
| ラジオ・録音スタジオ スピーチ用 | 15 | 20 | 15 |
| ラジオ・録音スタジオ その他 | 20 | 25 | 20 |
| テレビ・録画スタジオ スピーチ用 | 20 | 25 | 20 |
| テレビ・録画スタジオ その他 | 25 | 30 | 25 |
| アナウンススタジオ | 15 | 20 | 15 |
| 副調整室 | 25 | 30 | 25 |
| 主調整室 | 30 | 35 | 30 |
| エコールーム | 20 | 25 | NC-20の値 -6dB |
| エコーマシン室 | 25 | 30 | 25 |
| 事務室 | 35 | 40 | - |
| 録音室・会議室 | 30 | 35 | - |
| 廊下・ホワイエ | 35 | 40 | - |
図-5 室内騒音の許容値
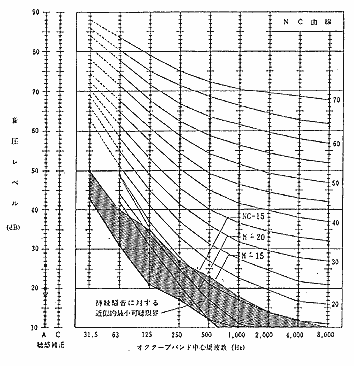
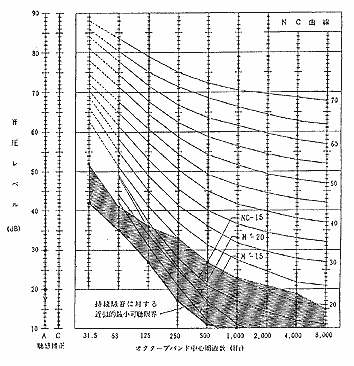
- スタジオ・メインフロア
- コントロール・ルーム
図-6 スタジオ暗騒音レベルの実測値(空調騒音)
(3) 距離減衰
広い空間では音は球面状に広がっていきます。その結果、音源から離れるにしたがって音のエネルギーは薄まり、 音源からの距離が2倍になるごとに全周波数帯域ともに6dBずつ減衰するのです。空気吸収により減衰するわけではありません。 したがって、閉空間である室内では、反射音(拡散音)の影響により一定のレベルにまでしか減衰しません。 また、ダクトの内部を伝幡する低音等は、ダクトの大きさに対して波長が長いため平面進行波となり、 ダクトの外へ抜けるエネルギー減衰以外、ダクト内の距離減衰はありません。
(4) 定在波
直接音が固い壁等からの反射音と2次元的に出会うと、位相干渉によるピーク、ディップを1/4波長ごとに生じます。 この現象を定在波と呼びます。ディップでは2つの音波の位相が反転しているために音圧レベルはほとんどゼロになり、 波長の長い低音では、ピーク、ディップの間隔が大きくなるために、音圧分布のムラが非常に顕著になります。 この現象を避けるためには、平行面をなくすか、波長に見合った拡散体を設けるか吸音処理を行うかが必要になります。
(5) 固有振動
音は球面状に放射されますから、室内には3次元までの定在波が生成されます。 したがって、部屋の大きさと同程度の波長をもつ低音域では、ピーク、ディップが3次元的に存在します。 これを固有振動と呼びますが、この現象はどんなに拡散性の良い部屋でも起こります。固有振動の周波数は、 室形状が直方体の場合、計算により簡単に求められます。例えば部屋の寸法比が2:2:1のように単純な比率の場合には、 固有振動の周波数分布のムラが大きくなり、特定の周波数でピーク、ディップが激しく生じますからスタジオの室内音場には好ましくありません。 そのために、部屋の寸法比を検討して固有振動の周波数分布をより一様にしようとするわけです。その計算結果の例を図-7に示します。
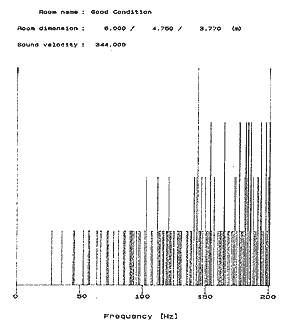
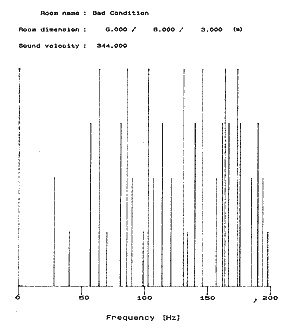
- 良い例
- 悪い例
図-7 固有振動の周波数分布の計算例
最も効果がある方法が、部屋の形状を不整形にする方法です。そうすることにより、1次元と2次元モードをなくして、 すべての固有振動が最も複雑な3次元のモードになるように考えるのです。スタジオ計画を行う場合、 できるだけ平行面をなくそうと考えるのはこういう理由によります。
(6) 遮音
音の伝幡を妨げることを遮音と言います。1重壁の場合、遮音には「質量則」と呼ばれる法則があります。 その実用式を (2)式に示します。
TL = 18Log(f・m) - 42.5 (2)式
TL;遮音量(dB) f;周波数(Hz) m;面密度(kg/m2)
この式からわかることは、周波数が高いほど、また面密度が大きいほど、 言い替えると重い材料ほど遮音性能が良いということです。したがって、遮音性能の特性は当然右上がりの直線になり、 同じ厚さであれば、合板より石膏ボード、石膏ボードよりガラス、ガラスより鉛板の方が遮音性能が良いわけです。 例えば、合板15mm、石膏ボード12mm、ガラス4mm、鉛板1mmはほぼ同じ遮音性能が得られます。 しかし、一方では、材料の厚さが2倍になっても遮音性能は 6dBしか上昇しないこともわかります。 厚さ150mmのコンクリート壁は50dB/500Hzの遮音性能をもっていますが、 厚さが2倍の300mmになっても 56dB/500Hzの遮音性能しかもたないのです。(図-8参照)
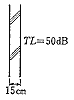 |
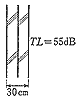 |
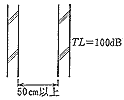 |
| (a)一重壁 | (b)二重に重ね合わせたとき | (c)独立に支持したとき |
そのために壁の間に空気層を設けた2重壁、3重壁として大きな遮音性能を得るのです。 例えば、厚さ150mmのコンクリートと石膏ボード30mmの間に空気層を100mm程度設けると65dB/500Hz程度の遮音性能を得ることができます。 石膏ボードも15mm×2枚だと 30dB/500Hzですが、同様に100mm程度の空気層を設けた2重壁にすると45~50dB/500Hz、 また3重壁にすると65dB/500Hzの遮音性能を得ることができます。
なお、現場での実際の遮音量は、(3)式に示されるように、遮音構造の遮音量(透過損失)だけではなく、 その遮音構造の透過面積と受音側の吸音力(受音室の吸音の程度)によって異なることを理解していなくてはなりません。
TL = P1 - P2 - 10Log(A / S) (3)式
TL;遮音量(dB) P1;音源室の音圧レベル(dB) P2;受源室の音圧レベル(dB)
A;受音室の吸音力(m2) S;音が透過する遮音構造の面積(m2)
(7) 吸音
あえて難しく言うと、音が材料に入射して内部を伝幡する際に、 その内部摩擦や粘性抵抗によって音響エネルギーの一部が熱エネルギーに変換されて消費される現象のことを吸音と言います。 そして、入射した音と反射して戻ってこない音のエネルギーの比を吸音率といいます。
よく勘違いされる質問のひとつに吸音材を用いて遮音できないかということがあります。 グラスウールに代表されるように、吸音性の高い材料は通常多孔質で透過性が高く、 また密度も小さいですからもともと遮音材としては機能しません。 確かに、うるさい機械室等では、吸音材を貼ることによって室内騒音レベルを低下させることができますが、 これは反射音による増幅分を抑える役目を果たしているだけなのです。 吸音効果による減衰量としては、吸音率が90%の場合でも10%は音として残り、10Log(0.1)= -10dBであり、 これと同じ効果を遮音で行おうとすれば 3mm程度の合板ですむわけです。
また、一般に用いられている吸音率の値は、 残響室内に実際に試料を設置して測定した「残響室法吸音率」と呼ばれるデータなのですが、 注意すべき点は、この値がエネルギー比であるということです。つまり、吸音率が90%の場合、吸音材に音が何度も入射することにより、 トータルの音響エネルギーとしては90%が吸音され10%しか残らないわけですが、その吸音面からの一次反射音の音圧は32%も戻ってくるという点です。 というのは、エネルギー吸音率と音圧反射率には(4)式に示される関係があるのです。
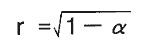 (4)式
(4)式
r;音圧反射率 α;吸音率
すなわち、仮に吸音率が99%だとしても、反射波の音圧は10%も戻ってくるのです。 完全吸音面を作ろうとしても難しいところはこのあたりにあります。スタジオでは意匠的な問題のために、吸音面の仕上げにクロスを使用しています。 そのクロスは、音響的に透過性の高い素材を使用していますが、それでもその表面からの反射音の影響を受けるのです。 つまり、その材質の特性によって色付けされた反射音によって音場は少なからず影響を受けてしまうのです。
一方、スタジオの響きはそのクロス内部の吸音処理によって調整します。そのためには、吸音のメカニズムを理解して、 その特性を生かした使い方が大切になります。図-9に、代表的な吸音構造とその吸音特性の傾向を示します。
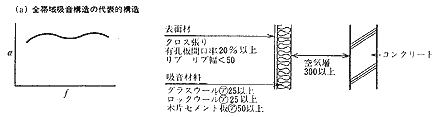
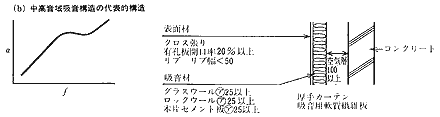
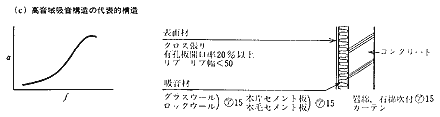
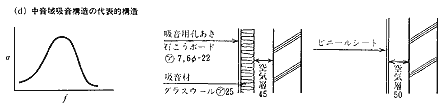
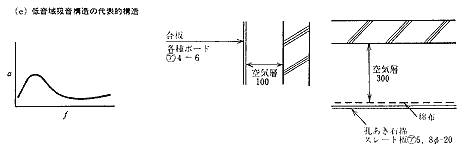
図-9 代表的な吸音構造と吸音特性の傾向
この図から分かることは、高音域の吸音には薄い吸音材で処理できますが、波長の長い低音域を吸音しようと思うと大きな空気層を必要とすることです。 そして、大切なことは、これらの吸音機構の組み合わせにより、1-2. で述べたような適切な平均吸音率が得られるように、 低音域から高音域までバランス良く吸音してあげることなのです。(図-3参照)
サウンドトラップは、合板の両側にグラスウールを貼付けて吊るしたものですが、 100Hz以上の帯域で比較的フラットな吸音特性が得られるので多く使用しています。しかし、偏った吸音機構の使い方をすると、 その特徴的な帯域だけが吸音されて不自然な音場となってしまうのです。
(8) 共鳴、共振
閉ざされた空間や有限の板状材料に音や振動等の外力が加わると、 その系が持つ固有の特徴的な周波数で振幅が極大値となります。この現象を共鳴、もしくは共振と言います。
共鳴の場合、その周波数のエネルギーを増幅させる一方で激しい空気振動を起こしますから、 その摩擦損失によって大きな吸音力を持ちます。そのため、残響の短い空間では残響付加装置のような働きをするし、 残響が長い空間では吸音装置のような働きをします。よく言われる能楽堂の舞台の下にあるカメはその両方の働きをしていたのです。
しかし、比較的残響が短いスタジオでは、共鳴による放射音の影響により抜けの悪い音になりやすいのです。 例えば、石膏ボードのような板状材料で遮音層、あるいは反射面をつくった場合、その背後の空気層の影響により低音域で共鳴を起こします。 ボード壁を叩いたときに聞こえる「ドーン」という音がその共鳴音ですが、この放射音の影響により音がこもり、抜けの悪い音場につながってしまうのです。 室内音場を考慮した場合、その影響をできるだけ抑えるために重量があり剛性の高い構造とした方が良いのです。
一方、遮音的にみると、この共鳴音と同じ帯域の音はそのまま透過する特性をもっています。 現実的には、そのまま抜けてしまうことはないのですが、その帯域では明らかに遮音性能が低下します。 この現象は「共鳴透過」と呼ばれます。また、ガラスや鉄板のように内部損失の少ない材質が、 音波により振動して主に高音域の特徴的な帯域で遮音性能が低下する現象は「コインシデンス効果」と呼ばれます。
(9) 浮構造
振動を遮断するために設ける防振構造を総称して浮構造と言います。 防振ゴム等によって床スラブ等の固定構造から浮いた状態となっていることからこの名があり、部位別に、浮床、浮壁、浮天井とも呼ばれます。
防振材料としては、一般的に浮床には防振ゴムかグラスウール、浮天井では防振ハンガー、 浮壁は通常地震時の横揺れ対策として防振ストッパーを用いています。
浮構造は大きくみるとひとつの共振系としてとらえられますが、 大切なのは防振効果がその振動系の固有振動数(f0)のおよそ2倍の周波数からしか発揮されないという点です。 例えば、通常使用される防振ゴムのf0はおよそ10Hzですが、31.5Hz帯域の防振性能は5dB程度、63Hz帯域で12dB程度しかないのです。 また、共振の項で述べたように、固有振動数の帯域では振動エネルギーは無限大まで増幅されてしまうのです。
浮構造の概念図、並びに固有振動数と振動伝達率の関係を図-10、図-11に示します。
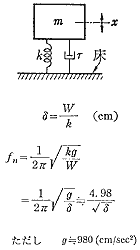
図-10 浮構造の概念モデルと固有振動数
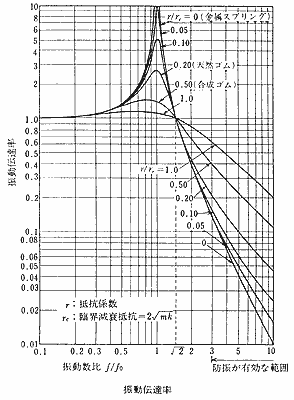
図-11 振動伝達率の周波数特性
一方、図-10からわかるように、固有振動数の計算式は簡単な式に簡略化されますが、 ポイントとなるのは浮構造の固有振動が防振ゴムのたわみのみによって決定されるということです。 すなわち、防振ゴムは適切なたわみ量の範囲内で使用しなければ規定の固有振動数は得られないのです。
なお、施工的な面からみると、浮構造と固定構造の間にはコーキング処理によるエキスパンションが必要になり、 浮構造を貫通する空調ダクトにはカンバスによる振動絶縁が、 また電気配管は遮音カップリングを用いるか振動を伝達しにくいCD管等を使用して配管を行う必要があります。
3. 音響計画上の制限
スタジオの計画を行う場合、音響的に自由な設計ができるわけではありません。 通常は、既存ビルの限られた建築条件の中で、また建築基準法や消防法などの規制の中でその計画を行わなくてはなりません。
以下に音響計画を実行する上での制約を述べてみたいと思います。
- (1) ビル構造の耐荷重
-
音楽スタジオを計画する場合、十分な静けさを得るために、通常「浮構造」を採用する必要があります。 そして、その構造は、前述したように、遮音的にも音場的にも重量があり剛性の高い構造としたいのです。 しかし、例えば、しっかりとした浮床を作ろうしてコンクリートを 120mm打設したとすると、それだけでも 280kg/m2の積載荷重がかかってしまうのです。
一般的なテナントビルの場合、床の許容荷重は 300kg/m2程度で設計されますから、ビルの構造上その構造は施工が不可能なのです。 そのため、床の許容荷重の範囲内で遮音構造を計画することが音響設計上の大前提なのです。 一般的に、ブロック等の重量構造を用いずに、石膏ボードによる乾式工法を多く用いるのはこういう理由によります。 しっかりした音響構造のスタジオを計画しようとすれば、500~600kg/m2程度の床強度が必要になります。
- (2) ビルの階高
-
スタジオ計画を行う場合、見落とされがちなのが空調機の設置スペース、また空調用のダクト、消音スペースです。 一般的に、空調の給排気は天井で行われますから、天井裏にこれらのスペースを確保する必要があるのです。 しかも、空調ダクト経由のクロストークや天井での吸音処理を考えると、このスペースは浮遮音天井の上部に確保したいのです。
例えば、浮遮音天井上部の空調ダクト、消音チャンバスペースを600mm、天井の吸音スペースを400mm、そして浮床を200mmだとして、 室内の有効天井高を2,400mm確保しようとすると、ビルの階高としては3,600mmの有効高さが必要になります。 ビルの階高は、高ければ高いほどスタジオ計画の自由度が広がるのです。
一般的なテナントビルでは3m程度の階高が多いのですが、この場合、大きな制約を受けることになります。
さらに、天井には梁がありますから、梁背が大きい場合、計画は大変難しくなります。 特に、空調のダクティングにあたっては、梁貫通がない場合必然的に梁の下を通さなくてはならないため、 室内の有効天井高はますます下がってしまいます。
- (3) 内装制限
-
スタジオを新設する場合、建築基準法や消防法等の法規を満足した計画を行わなくてはなりません。 音響的には、特に消防法の制約を大きく受けます。すなわち、排煙装置等の設備がない場合、仕上げ材や下地材を不燃材料で仕上げなければならないのです。
内装制限によって、不燃の仕上げ材で施工しなければならない場合、反射材として木材は使えませんし、 吸音面の仕上としてはガラス繊維を素材としたガラスクロスを使用しなければなりません。 前述したように、反射音は表面材の影響を受けますから、この時点で音場的な制約を受けてしまいます。 また、色の種類も少ないためデザイン的にも制約を受けます。一方、下地材も不燃でないといけない場合、 軽量鉄骨と呼ばれる軽い金属製の下地材を使用しなければなりません。したがって、木材に比べてしっかりとした下地が組めなくなりますし、 金属鳴りを起こすなど音場的にも好ましくないのです。
内装制限は、クオリティの高い音場計画を行う上で大きな制約となりますが、これを回避しようとすると、 その設置スペースの問題だけでなくコスト的に大きな負担となります。したがって、スタジオ計画を行う上で総合的な判断が必要になります。
4. まとめ
スタジオ音響設計の考え方について述べてきましたが、 やはり音響的に自由な設計ができた方がトータルクオリティの高いスタジオ計画につながります。 特に、計画するビルの条件によっては、前述したように大きな制限の中で計画を実現しなくてはなりませんから、 計画場所を決定した時点でその自由度が決まってしまうといっても過言ではありません。
したがって、スタジオを新設しようとする場合、スタジオ計画のコンセプトを明確にすることがまず大切ですが、 できるだけ早い段階でそのプロジェクトに音響専門会社を参加させた方が満足度の高い計画につながると思います。 共通の目標をめざしてディッスカッションを繰り返し、イメージをふくらませて具体化することが我々、音響専門会社の仕事であると考えています。
【参考文献】
※参考図の一部は以下の書籍から抜粋して使用しています。
- 「新版 建築の音響設計」 永田 穂 著 オーム社




