営業部 矢野 辰巳
1 まえがき
無響室は、各種音響測定のための基本的な設備です。以前は主としてマイクロフォンやスピーカなどの校正や特性測定に使われてきましたが、最近ではその他に聴覚の実験や各種機械類の騒音源からの放射騒音の測定など、広い範囲に使われるようになっています。
音響測定を行う場合、通常の部屋では、目的とする音よりも周囲の暗騒音の方が大きかったり、仮に静かな場所でも突発的に不必要な音が侵入して、うまく測定できない場合があります。
このような不必要な音をカットするためには、十分な遮音性能をもった材料で囲い、外部騒音を遮断する必要があります。
一方、囲まれたスペ-ス内では、反射音が多くて測定デ-タに影響を与え過ぎることから、不必要な反射音を極力カットするため、十分な吸音性能をもった材料で室の内部を仕上げることが必要になります。
このように、無響室とは測定被対象物からの音のみを測るため、反射音を少なくし、さらに静かな空間を得られるようにした室のことです。
2 無響室の種類
(1)完全無響室と半無響室
無響室は大きく分けると
- A) 完全無響室
- B) 半無響室
の2種類があり、使用目的により使い分けられています。室内表面の全て6面を吸音層で囲まれた部屋を完全無響室と呼び、一般的にはこれを無響室といいます。一方、床面または一面を硬い反射面とし他の5面を吸音面とした部屋を半無響室と呼んでいます。表1にその比較を示します。
表1 完全無響室と半無響室の比較
| 項目 | 完全無響室 | 半無響室 |
| 測定精度 | 高い | 完全無響室に比べやや劣る |
| 比較性能 | (1)音源及び受音点の設定が容易 (2)指向性測定が容易 |
(1)音源及び受音点の位置を正確に設定する必要がある。(測定位置で測定結果が異なる可能性がある。) (2)指向性測定が困難 |
| 作業性 | 歩行面が網状となるため、作業性はやや劣る | 床面が堅固であるため重量物の搬入、治具の取付等が容易 |
昭和61年に「無響室又は半無響室における音響パワ-レベル測定方法」(JISZ8732)が制定され、無響室と半無響室が定義されました。これは国際規格「無響室又は半無響室における精密測定方法」(ISO3745)の日本版ともいえるものです。
完全無響室は研究機関、弱電機器、精密機器、自動車部品、電気機器のメ-カ-等、精密測定を要求される部門で使用されています。また、半無響室は、産業機器、自動車、汎用機器、電気機器メ-カ-等、大重量や付帯設備の多いものを測定するのに使用されています。
(2)吸音性能による種類
無響室の吸音構造は以下に示す2種類に大別されます。 表2にその比較を、図1にその外観図を示します。
- A)吸音楔式
- B)多層式
- 表2 吸音楔式と多層式の比較
-
項目 吸音楔式 多層式 遮断周波数 125Hz※ なし データの信頼性 大きい(遮断周波数以上で) 小さい 汎用性 大きい 小さい ラベリング 精密級で可 実用級で可 規格 ISO3745
JIS8732ISO3744
※楔の長さ600mmの場合 -
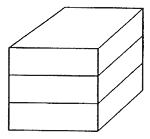
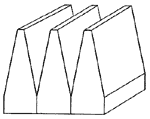
- 吸音楔
- 多層式
-
A)の吸音楔構造は、(1)公的機関に音響データを発表する場合、(2)輸出品にラベリングする場合、(3)高い測定精度を要求される場合等に使用され、低周波帯域からの測定が可能です。
B)の多層式構造は、(1)自社内での製品検査、研究開発、(2)数多くの無響室を設置する等、ある程度比較測定で可能な場合に使用され、主に、中、高周波数帯域の測定が中心となります
| 名称 | 概略断面図 | 特徴 | 主なユーザー |
|---|---|---|---|
| 完全無響室 |  |
精密測定が可能 | 研究機関 弱電機器 自動車部品 |
| 完全無響室 リフター付き |
 |
試験体下部の測定が可能 | 自動車部品 |
| 完全無響室 移動床付き |
 |
全無響室と半無響室の二つの機能を有する | 産業機械 自動車部品 汎用機 |
| 完全無響室 定盤付き |
 |
振動を有する測定対象物の精度を上げた | 自動車部品 自動車エンジン 産業機械 |
| 完全無響室 残響室付き |
 |
音材料の測定及び吸音材 | 遮音材料 自動車部品 |
| 半無響室 |  |
重量の大きな試験体の測定 | 産業機械 自動車 自動車部品 汎用機 |
| 半無響室 一部完全無響 移動床付き |
 |
小部品を完全無響の状態で測定し、床を戻すことにより半無響室を広いスペースで使用できる | 自動車部品 汎用機 |
| 半無響室 一部完全無響付き |
 |
小部品を完全無響の状態で測定を行える | 自動車部品 汎用機 |
3 無響室のバリエーション
(1)概要
無響室の様々にある形態のうちから、いくつかを表3に示します。
このように完全無響室、半無響室といった単純な形態だけではなく種々の無響室が世の中にあることが分かります。
次に、当社で施工させていただいた無響室の例をいくつか挙げて、その特徴や使われ方などについて少し触れてみます。
(2)床歩行面が2面ある無響室
この無響室は昭和62年に竣工したもので、某機器メ-カ-の一見すれば普通のタイプの実験室です。その断面を図2に示します。図に示すとおり床歩行面が2段になっており、被測定物の下部からも測定できる特徴を持っています。そのため、床歩行面は可能なかぎり反射を少なくするためにステンレスワイヤを採用しています。
この無響室ではパワ-レベル測定だけでなく、聴感実験にも使われ、各種機器の騒音特性がいろいろな方面から測定され、その低減化に役立っています。
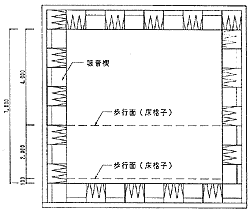 図2 無響室断面図
図2 無響室断面図
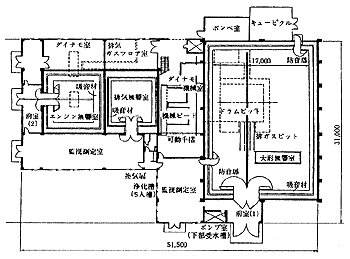 図3 自動車騒音実験棟平面図
図3 自動車騒音実験棟平面図
(3)大型半無響室
この大型半無響室は昭和51年に竣工したもので、自動車の一般走行状態を再現し、その音響特性を把握する施設として計画されました。この概要を図3に示します。
従来、車輌の自動車騒音試験を行う場合、静かな環境と周辺に反射物が無いことが条件となり、屋外で測定が主となって、測定の実施が天候に左右されていました。
この半無響室はとにかく広いのです。床面がコンクリ-トで反射性、その他の面が吸音層で覆われてた半自由空間であり、有効寸法は17m×24mもあります。(テニスもできる?)
この無響室には通常の無響室と違って、シャ-シダイナモや特殊な空調設備等の付属設備があります。 シャ-シダイナモは車を動かさないで走行状態を実現する装置で、ここでは、大型車用と小型車用の2種類のシャ-シダイナモが設置されています。空調設備は、温度および湿度を一定状態にするための設備と、騒音試験を行う場合に発生するタイヤからの発熱や排気ガス等を除くための設備があります。
この無響室では、ダイナモ上に車を固定して、定常走行騒音・加速騒音などが測定できます。また、広い空間を有しているので騒音の放射特性も測定可能です。
(4)移動床付きの完全・半無響室
この無響室は昭和62年に竣工したもので、コンクリ-ト製の自動式スライド反射床を備え、測定精度の良い無響室として、また供試体の設置に有利な半無響室としても使えるようになっています。無響室平面図を図4に示します。
この無響室は乗用車の排気騒音を主に測定する目的で計画されたもので、実車を搬入しての測定も可能となっています。スライド反射床は操作室・計測室の床下に収納され、収納時には完全無響室となります。
完全無響室として排気騒音を規格に従って測定するだけでなく、歩行床が二重になっているので、排気管下部からの測定もできます。また、実車を完全無響室に搬入することができるので、より精密な測定も可能です。
半無響室としては床面が強固なため排気管等の支持が容易であり、排気管やマフラ-の自動車への固定位置を決める作業を簡単に行うことができます。また、床面からの反射音を含んだ排気管や実車の実際の騒音を把握することもできます。
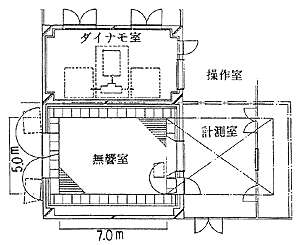 図4 移動床付き無響室平面図
図4 移動床付き無響室平面図
(5)残響室との間に開口部を持つ無響室
この無響室は平成元年に竣工したもので、完全無響室としてだけでなく、隣の残響室間に試料開口部を設けることが出来るようになっています。この実験室は建設会社の技術研究所内につくられたものです。平面図を図5に示します。
この無響室の大きな特徴は、無響室単独の使用のほか、無響室内部の残響室側の壁の一部分が移動式吸音扉になっており、残響室・無響室間に試料用開口を設けることが簡単にできることです。さらに、試料は作業ヤ-ドにある移動装置(台車)上に施工して、残響室・無響室間に挿入します。透過損失等の測定が簡単に、かつ連続的にできるようになっています。また、通常の残響室・残響室法では不可能な音響放射特性(建材のどの部分からの音漏れが大きいかなど)を測定することができ、より多くの情報を得ることが可能となっています。
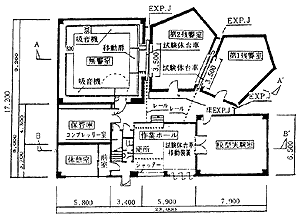 図5 残響室との間に開口部を持つ無響室
図5 残響室との間に開口部を持つ無響室
4 あとがき
このように世の中にはいろいろな顔を持った無響室があることがわかっていただけたと思います。紙面の都合で、載せられなかった色々な特徴を持つ無響室もありますので、特殊な用途、特殊な測定等を計画をお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。




