技術部 北浦 季之
本業務は騒音源の対策を検討されている企業様向けのサービスです。
個人で騒音にお困りの方、騒音の相談を受けている管理会社の方向けには対応しておりませんが、こちらが参考になれば幸いです。
1. はじめに
夏真っ盛り、いかがお過ごしでしょうか。暑い夜など窓を網戸にして眠りたいものですね。 最近はエアコンの普及で、あまり窓を開けて寝る人は少なくなっているようですが、外部の騒音、特に深夜の交通騒音は気になります。 もしあなたが一生かけての買い物としてマンションを購入したとき、交通騒音がやかましくて睡眠不足になったら悔しくて余計に眠れなくなるでしょう。 それもちょっと無理して購入した物件ならなおさらです。
そんな苦情の出ないように、建築工事の前に十分な検討が行われる必要があります。 今回ご紹介させていただくのは、それらの検討のため、事前の交通騒音の測定から、 特に外部の騒音が侵入してくるであろう窓サッシの仕様選定までの一連の流れを簡単にまとめたものです。
快適な生活を送るには周到な準備が必要です。交通騒音測定はその一端に過ぎませんが重要な役割を持っているのです。
2. 道路交通騒音測定の目的
道路交通騒音の測定は主に二つの目的に別れます。一つは前述したように特定の場所で集合住宅等の窓仕様を検討する資料などとする場合。 もう一つは地方自治体などにおいて地域を代表する場所で騒音レベル自体を行政目的で計測する場合があります。
2-1 行政目的の測定の場合
「騒音に係る環境基準」の達成状況の把握のための測定、「騒音規制法」に基づく指定地域についての騒音の測定、 各自治体における「公害防止(環境保全)条例」等による測定など、法令に基づいて交通騒音の測定を行い、今後の対策を立てたり規制の検討を行います。
期間は、通常1週間のうちの平日5日間を24時間づつ測定し、地域の数箇所で同時に行います。 特定の建築物等を対象とするでのはなく、地域を代表する場所での騒音レベルを把握します。
なお、測定点(マイクロホンの位置)の高さは、地上1.2m~1.5mで行います。
2-2 窓仕様検討等のため測定する場合
-
測定点は建築予定敷地内で行います。より具体性をもたせるため、 最も騒音レベルの高くなるであろう2階の窓付近(高さは地上5m程度)にマイクロホンを設置します。 付近に騒音を遮蔽するような建築物があり、予定建築物がそれよりも高い建物になる場合はクレーンや気球を使ってより高い地点で測定することもあります。
測定は原則として、一昼夜24時間行いますが、建築工事がすでに始まってしまっている場合は、 工事をしていない夜間から朝にかけて測定を行います。睡眠時の静寂を確保するための測定ですから、データも夜間のものを重視して窓仕様を検討します。 昼間の騒音を対象にしますと、オーバースペックになりがちで後述する近隣騒音に悩まされることにもなりかねません。
以上2通りの測定がありますが、今回は後者について述べさせていただきます。
3. 測定
3-1 測定方法
まず測定点の周辺を地図であたり、騒音源をさがします。敷地真横に幹線道路など大きな騒音源がある場合、 測定点の位置が重要になりますので測定の準備段階で設計図面などから正確な距離を出します。 また、測定場所の事前情報も必要です。新築工事の現場であれば測定の開始時刻や測定点の位置、 撤収時間や機材の置場所などは現場管理の方との打合せを忘れてはなりません。 測定場所が更地の場合は機材の保管に留意し、測定のための電源(自動車のバッテリなど)を確保する必要もあります。 さて、機材の準備にかかります。
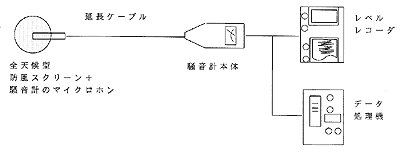
図1 測定機器ブロックダイヤグラム
測定機材のブロックダイヤグラムの一例を図1に示します。騒音計・レベルレコーダ・データ処理機が主な測定機です。 騒音計は通常本体とマイクロホン部とを延長ケーブルでつなぎます。測定前に延長したままピストンホン(外部校正信号機)で校正しておきます。 ピストンホンと騒音計の内部校正信号の出力は必ずしも一致しないのでレベルレコーダ、データ処理機ともに校正しておき、 ピストンホンと内部校正信号との差を記録しておきます。そうすると現場で内部校正信号のみでの校正が可能となり、設置時間の短縮ができます。
機器の準備が整い、接続ケーブル、電源ケーブル、バッテリなどを用意し終わったら機材チェックのあと天気予報を確認します。 小雨程度の場合や風も強風でない限り測定は行います。
現場に到着後、まず天候・風向風速・温湿度を計測し、マイクロホンの設置を行います。 目的のところで触れましたように5mの高さに設置します。その際はポール・竿などを使いますが、倒れないように重りをつけ、固定します。 その際、延長ケーブルをひきまわしますが建築現場では重機やトラックに潰されないように留意しています。 次に、記録機器関係の設置をします。ここで各機器に関する騒音測定時の留意点をまとめてみます。
(1) 騒音計
- 測定レンジが適当か?あまり大きすぎても小さすぎてもいけませんが、いつどんな音が入ってくるのかわからないのも事実。 一度10分程度測定してから決定します。
- 周波数特性補正回路がA(dB(A))か?騒音計にはA、C、Fの周波数補正回路が備わっています。 Aの回路は騒音レベル(dB(A)、いわゆるホン)を測定するものです。 騒音レベル=dB(A)とは、人間の耳の特性に近い周波数特性の重みづけがしてあります。環境基準もこの値を使用します。 簡易的な窓仕様の検討ならばdB(A)の値だけでの検討も可能です。
- 電池のチェック。無人測定の場合、単3のアルカリ電池で24時間以上駆動可能です。必ず新品と入れ替えます。
(2) レベルレコーダ
- 校正信号:校正信号がセットレンジ+4dBにレベルを書き出すように設定します。
- 紙送りの速度:一般的には秒速1mmもしくは3mmで送りますが、 無人でデータ処理機を併用している場合には秒速0.1mmもしくは0.03mmで送っています。 また、電車が近くを通過している場合は通常の紙送り速度で送り、電車のピークレベルを測定します。
- 記入事項:測定日時、測定場所、測定レンジ、測定点名、紙送り速度、主な騒音源、特殊な騒音(飛行機、救急車のサイレンなど)を記入します。 特に時刻は秒単位まで(00分00秒が望ましい)記入します。周波数特性補正回路(dB(A)など)の表記も必要です。

基本的にこの二つの機材を中心として測定を行いますが、 交通騒音の評価は「不規則かつ大幅に変動する騒音」として統計分析によって評価されます。 この統計分析を行うデータ処理機とレベルレコーダを併用して測定を行いますと、騒音レベルの変動とともに1日の最大最小値がわかり、 迅速な処理が可能です。測定は15分~1時間おきに100~500個(1~5秒間隔)の騒音レベルをサンプリングし、統計処理を行います。
また、当社のポータブルデータ測定システムDL-80/PTを利用すると周波数特性も同時に測定することが可能となります。
3-2 騒音の評価
前述したように騒音の評価はJIS Z 8731「騒音レベル測定方法」に準拠して行います。 道路交通騒音のように「大幅かつ不規則に変化する」騒音は「時間率騒音レベル」として評価します。JISから引用しましょう。
【時間率騒音レベル Lx】
騒音レベルがあるレベル以上である時間が実測時間のx%を占める場合、そのレベルをxパーセント時間率騒音レベルという。 単位はデシベル、単位記号はdB。
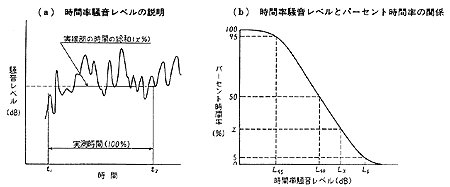
図2 時間率騒音レベルと時間率
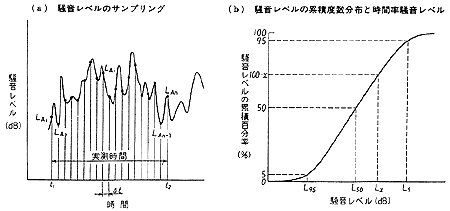
図3 時間率騒音レベルと騒音レベルの関係
なお、50パーセント時間率騒音レベルL50を中央値、5パーセント時間率騒音レベルL5を90パーセントレンジの上端値、 95パーセント時間率騒音レベルL95を90パーセントレンジの下端値などという。
また、測定方法について(時間率騒音レベルLxの求め方(1983年改定版))は、 騒音計などを用いて一定時間間隔△tごとのサンプリングによって騒音レベルを測定する。 その場合、騒音計の動特性としては、速い動特性(FAST)を用いる。また、サンプリングの間隔は5秒以下とし、 少なくとも50個以上のサンプル値を求める。ただし、サンプリングの時間間隔を短くした場合でも、測定時間は数分以上とする必要がある。(中略)
このような統計処理の仕方としては、従来広く行われているように、 手作業によって騒音レベルのサンプル値について値が小さい順に1dBごとに個数を数え、 その累積度数を求めて累積度数分布曲線を描き、それから所定の時間率騒音レベルを読みとる方法を取ってもよいが、 最近広く普及しているデジタル形の統計処理機や汎用のコンピュータを用いれば、種々のLxに加えてLAeq,T(等価騒音レベル)も容易に求めることができる。
なお、変動騒音の代表値としてL50などの時間率騒音レベルなどを求める場合にも参考値としてLAeq,Tも求めておくことが望ましい。
以上の方法によって騒音の測定・評価が行われます。窓サッシの検討は主にL5,L10のいずれかのデータによって検討されています。 その理由は、最大値では過剰性能の可能性があり、平均値では過小評価の可能性があるからです。
1日24時間のL5,L10は時間帯によって変動しますので、時間帯を朝、昼間、夕、夜間の4つに区分し、 その夜間(午後9時、10時又は11時から翌日の午前6時又は7時までで、時間区分は「騒音規制法」に準拠しており、 対象となる都道府県により異なります。)の時間帯中で最大の値を示した時間のデータが室内騒音を計算する場合の「外部騒音レベル」としています。
次の章で、窓仕様を決定するための室内騒音レベルの一般的な計算方法を紹介します。
| 建築物 | 室用途 | 騒音等級 | 騒音レベルdB(A) | ||||
| 特級 | 1級 | 2級 | 特級 | 1級 | 2級 | ||
| 集合住宅 | 居室 | N-25 | N-30 | N-35 | 30 | 35 | 40 |
| ホテル | 客室 | N-30 | N-35 | N-40 | 35 | 40 | 45 |
| 事務所 | 一般事務室 | N-35 | N-40 | N-45 | 40 | 45 | 50 |
| 事務所 | 会議・応接室 | N-30 | N-35 | N-40 | 35 | 40 | 45 |
| 学校 | 普通教室 | N-30 | N-35 | N-40 | 35 | 40 | 45 |
| 病院 | 病室(個室) | N-30 | N-35 | N-40 | 35 | 40 | 45 |
| 戸建住宅 | 寝室 | N-25 | N-30 | N-35 | 30 | 35 | 40 |
| コンサートホール、オペラホール | N-20 | N-25 | N-30 | 25 | 30 | 35 | |
| 劇場、多目的ホール | N-25 | N-30 | N-35 | 30 | 35 | 40 | |
| 録音スタジオ、ラジオスタジオ | N-20 | N-25 | N-30 | 25 | 30 | 35 | |
| テレビスタジオ | N-25 | N-30 | N-35 | 30 | 35 | 40 | |
予測対象室:1階居間 音源:高速道路、道路端
| 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | dB(A) | 備考 | |
| 外部騒音 (Lo) | 59 | 65 | 70 | 70 | 69 | 61 | 75 | 二重ガラス FL3+A50+FL6 カーペット敷 天井高 2.4m
|
| 壁の透過損失 (TL1) | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 72 | ||
| 壁の音響透過率 (τ1) | 4E-05 | 1E-05 | 3E-06 | 1E-06 | 3E-07 | 6E-08 | ||
| 壁の面積 (S1) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||
| 窓の透過損失 (TL2) | 15 | 27 | 38 | 48 | 51 | 55 | ||
| 窓の音響透過率 (τ2) | 3E-02 | 2E-03 | 2E-04 | 2E-05 | 8E-06 | 3E-06 | ||
| 窓の面積 (S2) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
| 平均音響透過率 (τ) | 1E-02 | 9E-04 | 7E-05 | 7E-06 | 4E-06 | 1E-06 | ||
| 総合透過損失 (TL) | 19 | 31 | 42 | 51 | 54 | 59 | ||
| 平均吸音率 (α) | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | ||
| 総表面積 (S) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| 吸音力 (A) | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | ||
| -10 log A | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| +10 log Si | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 室内音圧レベル (L) | 43 | 36 | 30 | 21 | 17 | 4 | 33 |
平均音響透過損失(τ)τ = ΣSiτ1 / ΣSi = (S1τ1 + S2τ2) / (S1 + S2)総合透過損失(TL)TL = 10 log (1 / τ)
S1、τ1:外壁の面積(m2)及び音響透過率 S2、τ2:窓の面積(m2)及び音響透過率
窓の透過損失(TL1):二重ガラス;3mmガラス+空気層50mm+6mmガラス
(「板ガラスの遮音性能」板硝子協会(1998)より)壁の透過損失(TL2):RC250mmとした場合のランダム入射の透過損失各音響透過率(τ1、2=τiとする)τi = 10 (-TLi / 10)室内音圧レベル(L)L = Lo - TL - 10 log (A) + 10 log (S) + 6
Lo:建物がない場合の室外の音圧レベル(dB)
吸音力(A):総表面積(S) × 平均吸音率(α)[m2] 部屋内を拡散音場とする。
4. 対策の検討
4-1 開口部の遮音対策(室内騒音レベルの算出法)
Lx法で得られた、L5もしくはL10の周波数測定結果から室内騒音レベルを予測します。 まず、目標とする室内騒音レベルもしくはN値を表1により決定します。次に騒音の測定点と窓の位置が離れている場合、 距離減衰の計算を行いますが、窓付近を想定して測定を行った場合は割愛します。表2に計算例を示します。
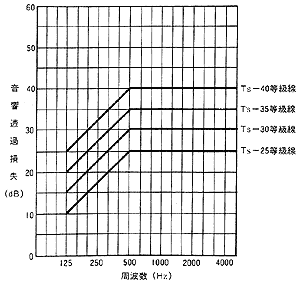
図4 JIS A 4706 の遮音等級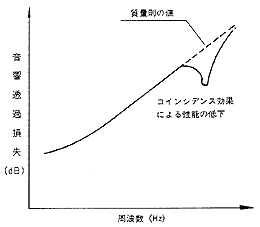
図5 コインシデンス効果
4-2 Ts値について
以上の計算によって窓サッシの選定をするわけですが、お客様から「Ts値」を聞かれる場合があります。
JIS A 4706(アルミニウム合金製及び鋼製サッシ)には防音サッシの等級線が規定されています。 防音タイプのサッシのカタログには透過損失の周波数特性が掲載されていない場合がありますが、Ts値は必ず記載してあります。 ただし、Ts値は目安としての曲線であり、防音技術標準ではなく、製品規格です。JISではこの曲線を実測値が下回らないことを要求しています。
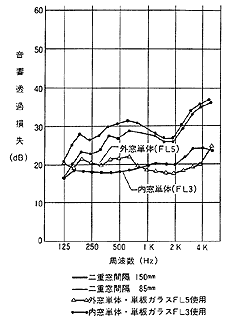
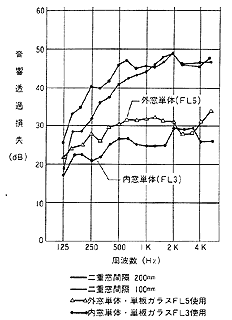
- 図6 独立枠二重窓
(普通サッシ)の遮音性能 - 図7 独立枠二重窓
(防音サッシ)の遮音性能
また、多くの防音サッシでは中低域周波数の透過損失がTs値を上回っても、2kHz周辺で性能が落ち込む性質を持っています。 これはガラスのコインシデンス効果と呼ばれるものです。
コインシデンス効果は資材の材質によって様々な周波数で発生します。ここでは詳細は省きますが、 ガラスの遮音上の弱点が2kHz付近にあるということになります。
4-3 2重サッシについて
前述したガラスのコインシデンス効果を軽減させ、遮音性能を向上させるには窓を2重にする、という方法があります。 航空機の飛行コース直下や高速道路に隣接している敷地、鉄道に隣接している敷地などに建築される建物の窓には有効です。 ただし、窓の間隔が数ミリ程度では中低音域で共鳴透過という現象が起こってしまい透過損失が減少してしまいます。
なお、予算と空間に余裕があれば、独立型の2重サッシをお進めします。窓の間隔(空気層)は10cm以上とり、 中を吸音します。(有効板の下にグラスウールなどの吸音材を詰め込むなど)窓ガラスの厚さは外側を厚く、内側を外側より薄くします。 すると、質量則(質量に応じて遮音性能が向上するという性質。材質によって様々。)に沿うような壁の遮音性能に近い特性となっていきます。
4-4 サッシの選択の問題点
サッシには実に様々なタイプがあります。普通サッシ、防音サッシ、エアタイト、複層、一体型2重サッシ、独立型2重サッシ。 以上は防音の観点から遮音性能の低い順に並べてみたサッシの種類です。よく金網が入っているガラスを見かけますが、遮音性能にはほとんど効果はありません。 また、サッシ(窓枠)にも木製、スチール、アルミ、塩化ビニールなどの種類があります。隙間を埋めやすい塩化ビニール製が遮音性能上は良いようです。 しかし、いくら最高のガラスとサッシを使用したところで、施工精度がお粗末ではどうしようもありません。音はわずかな隙間から侵入してくるのです。
もうひとつ、大きな問題があります。それは、集合住宅で時折あることなのですが、 窓のグレードを不必要なほど高く設定して外部騒音をほとんど遮断した場合、隣近所の建具の開閉音、給排水音、 歩行音などのいわゆる近隣騒音が壁や天井や床からやけに聞こえてくることがあります。もっとも、それらの近隣騒音が聞こえることに問題があるのですが、 多少は外部騒音が侵入したほうが近隣の騒音を覆って、お隣さんと喧嘩をしなくても済むかもしれません。
5. まとめ
ここまで、道路交通騒音の測定から評価、対策についてお話してきました。人が便利さを追求すれば、交通騒音から逃れることは不可能です。 窓を無くして壁ばかりの部屋ならば、かなりの遮音量を稼げますが快適とは程遠い住環境になってしまいます。 やはり、行き着く所はバランスということでしょう。外部と室内の騒音レベルのバランス、予算と選べるサッシとのバランス。 これらのバランスが崩れたとき、問題が起こります。もしバランスが激しく崩れると、病気になる人さえ出てきます。 私達の日頃行っている交通騒音測定は、快適・便利と不快・不便とのバランスを求めて行っているのかもしれません。
今後とも、より快適な住環境(特に音環境)の創造を目指して、 測定精度のさらなる向上と迅速な対策の検討ができるよう努力していきたいと考えています。
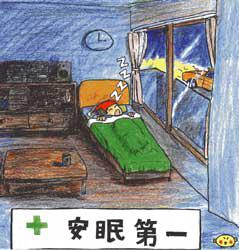
【参考文献】
窓と防音(改訂版) 1989年 板硝子協会 建築技術別冊「住宅の防音と調音のすべて」1988年12月 建設省建築研究所 監修
本業務は騒音源の対策を検討されている企業様向けのサービスです。
個人で騒音にお困りの方、騒音の相談を受けている管理会社の方向けには対応しておりませんが、こちらが参考になれば幸いです。




