営業部 肥後 信雄
1 はじめに
今回、無響室の歴史、主に当社の無響室工事の変遷を紹介させていただきますが、それに先立ち当社発足までの経緯を簡単に述べさせていただきます。
当社の元々の始まりは、親会社に当たる日東紡績(株)が、昭和16年に日本で始めてロックウール(岩綿)を商品化したことにあります。
戦時中は潜水艦等の、戦後は建築用の断熱材としての材料販売が主でしたが、ロックウール、グラスウールのシェア拡大と新たな価値を付加するため、防音、吸音材料としての利用を図り、昭和28年頃から日東紡績に音響部門がスタートし、無響室用吸音楔の製造や、騒音対策の相談を受けたり、少しづつ音の分野への仲間入りのきっかけを作って行きました。
昭和30年代に入って、無響室を東京大学や日立製作所、等で施工させていただきましたが、諸先生方のご指導を仰ぎながら、音響理論はある程度理解できても、施工技術はまだまだ未熟で、責任施工と言うには遠い状態でした。そのため、当時の「茂田設計」に設計や現場管理などの協力を得て事業を進めていましたが、皆様からの音に対する様々な要望への対応や、設計施工(管理)体制の確立のため、昭和36年に日東紡績に「建材部音響工事課」が設置されました。
一方、茂田設計も、社名を「(株)ニチオン」と改め、音で生きる道を歩き始め、音響に係る設計や工事を専門的に行うようになりました。
その後、様々な経緯はありましたが、日東紡績とニチオンが共同して、音に徹底的にこだわりを持ち、音を追求するユニークな会社となることを目指して、昭和49年4月に日東紡音響エンジニアリング(株)が発足しました。
それから早20年、今日まで曲がりなりにも来れましたのも、御得意様、諸先生方、協力会社の皆様のご支援の賜物と、誌面をお借りしまして厚く御礼申し上げます。
当社の経歴が大変長くなりましたが、今回の主題であります「無響室の歴史」を紹介させていただきます。
2 無響室の先輩
無響室の設置は、欧米が最初で、デンマークの工科大学、ドイツのBMW、アメリカのIBM、GMゼネラルモタース、フォード、クライスラーなどが先駆者として、早くから音に取り組み、各分野での製品の研究開発、また規格化のため、無響室を利用していました。
それらを日本へ技術導入して、昭和10年代に東京大学航空宇宙研究所(駒場)に始めて無響室が設置されました。その後、武蔵野電気通信研究所、東京大学(千葉)、電気通信総合研究所(三鷹)、日本放送協会(NHK)などに作られましたが、昭和10~30年前半までは完全無響室(6面体吸音層)のみで、音の研究も、大学、電気通信、放送と限られた分野だけで行われていました。
3 当社が施工した無響室の変遷
(1) 昭和30年代~40年代の無響室
当社がスタートした直後で、需要も少なく、よちよち歩きの状態でした。特に施工体制もないまま、主に大工さんと鉄工屋さんを頼りに工事を行っていましたが、そのなかでも、いくつかの工夫や改良を積み重ねられたと考えています。 昭和35年に施工したある電気メーカーの完全無響室では、次のような改善を行いました。
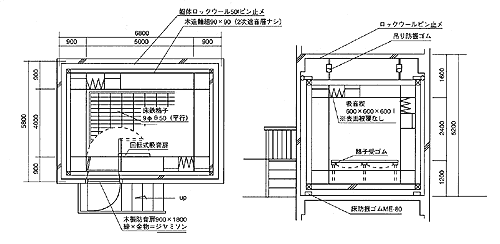
図-1 昭和30年代に施工した無響室の概略図
それは、図-2に示すとおり、木表防音扉の表板(鏡板)、床格子のポスト受ゴム、建具の締めハンドルなどですが、特に、ハンドルについては、完成近くにお客様を案内して室内に入り、ジャミソンハンドルの押棒を押したらボキッと折れてしまい、外に出られずハンドルを取り外してようやく脱出できたいうことがあり、それを機会にローラハンドルの採用を決めたものです。他にもまだまだ改善することが一杯あると痛感していた時代でした。
| 図-1の構造 |
|---|
1.木製防音扉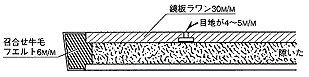 |
2.床鉄格子の受ゴム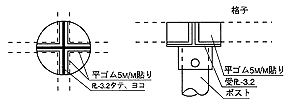 |
3.防音扉の締め金物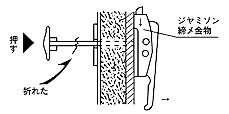 |
| 改善後の構造 |
|---|
1.木製防音扉 |
2.床鉄格子の受ゴム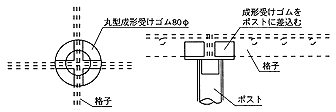 |
3.防音扉の締め金物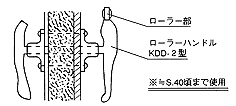 |
図-2 図-1に示す無響室の主な改善点
この時代の無響室の設置は、主に官公庁や大学の研究機関が主流でしたが、30年代後半からは、自動車、家電メーカー等の需要が増えてきました。それまでの無響室は殆どが完全無響室でしたが、自動車メーカー研究所の無響室は、実際の走行と同じ状態とするためのシャーシダイナモを付けるため、半無響室(5面が吸音層で床面が反射面)とするなど、特殊な無響室も作るようになりました。
また、30年代後半になりますと、当社が行う工事範囲も内装工事から空調、電気設備も含めた全体をまとめることが増えて来ましたので、それまでの音響、建築の知識に加え、設備の関連知識が必要とされ、周辺技術の習得に努めました。

(2) 昭和40年~60年代の無響室
この年代になりますと、従来の需要先に加え、工業高校関係やオーディオメーカー、また大手建設会社の研究所と種々の業種で無響室を設置するようになりました。
当社が行う設計・施工の範囲も広くなり、空調電気設備ばかりでなく、自動車メーカーの場合、エンジン排気ガスの給排気、熱処理、機器の冷却、また計測用の付帯設備として、監視用TVカメラ、コネクターボックス、給排水、エアー、オイル配管、ターンテーブル等々と対応も幅広くなってきました。
また、無響室の構造も木造から鉄骨に不燃化されてきたのもこの時代です。
40年代後半から、自動車メーカーを始めとするの半無響室の建設が多くなりました。この頃に施工した大型半無響室((財)日本自動車研究所)では、設計当時、拡散理論から音場予測(逆二乗則の成立)を行っていましたが、実測すると予測値よりも音圧が低くなることがあり、原因がわからず苦労したことがありました。そのため、音の干渉(位相)に注目した半自由音場の予測方法の検討を行い、ようやく実測にほぼ一致した結果を得ることができました。この時の苦労により、まだ完全とは言えませんが(楔の斜入射吸音率を導入するまでには至っていない)、現在では音場を設計時に概ね予測することができ、経済的な設計に役立たせています。
(3) 昭和60年代から現在の無響室
60年代になりますと、当社の施工工事も、ほとんどの無響室が内装から防音建具、空調電気設備、さらに音響測定までとトータルな形での責任施工が多くなってきました。そのため、現在も、協力会社も含めたグループとして体制の強化に努めております。
また、無響室の種類も多用途化の中で、これまでの完全、半無響室だけでなく、完全無響室の床板を移動させて半無響室として機能も発揮出来たり、また無響室と残響室の組み合わせで諸材料の遮音特性も計測出来る室にするとか、多機能、多目的化の傾向になっています。
さらに、最近では音と電波を組み合わせた形で、電波暗室と無響室を結び付け、一つの室で両機能を発揮させるものが作られています。
今後は、吸音体+吸音楔が1本または1枚で両機能を発揮できるものが現れるのも近いのではと期待しています。
当社では、あらゆるニーズにマッチした測定空間(無響室等)だけでなく、そこでの計測システムも提供させていただけます。
50年後半から当社で開発を始めたマイクロホン移動装置とコンピュータ-を連動させた自動計測システムが、最近の無響室の必要設備となっています。

4 吸音楔の種類と特性の変遷
無響室で最も重要なものである吸音楔について、その内容の変遷をまとめると表-1のようになります。
表-1に示すとおり、吸音楔もこれまで色々な形、寸法、素材の種類、密度、表面の仕様材の検討が重ねられましたが、現状では、グラスウール32Kg/m3が最も優れていると考えられます(表面の被覆材の無い方が尚良い)。楔として理想的には、繊維太さが5~7μでノーバインダーの繊維が十分に絡み合っていて、充填むらなく仕上げれば、さらに吸音特性は改善されると思います。
| 楔の寸法と種類 | 構造 | 特性 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 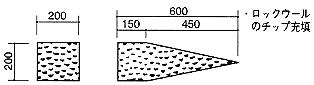 |
・素材=ロックウール30H/H程度のチップを充填 ・フレーム枠=ユニクロメッキ ・表面仕上=薄手布被膜 |
・充填ムラが生じ低音域に難あり |
| 2 | 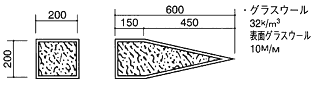 |
・素材=グラスウール32K/m3成形板加工 ・フレーム枠=ユニクロメッキ ・表面仕上=グラスウール10H/H |
・グラスウールの成形時の接着剤が多少多いため低音域にやや難あり |
| 3 | 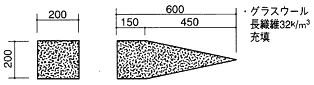 |
・グラスウール長繊維(5~7H)32K/m3充填 ・フレーム枠=ユニクロメッキ ・表面仕上=クレモナ布被膜 |
・開繊~充填ムラが生じ低音域に難あり |
| 4 | 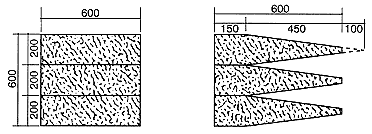 |
・素材=グラスウール32K/m3成形板加工 ・フレーム枠=ビニールコーティング ・表面仕上=コーデラン布メッシュで被膜 |
・接着剤の量を注意すれば性能が保たれる |
| 5 | 多層式(現場施工)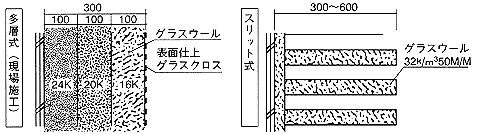 |
・主な用途=簡易無響室、テスト室、学校等 ・設計値によって十分利用出来、又コストも経済的 |
|
| ・吸音楔の長さは設計値により決めます。 ・上記の種類、仕上以外にも設計できます。 |
|||
表-1 吸音楔の種類と構造(特性)
また、吸音体の素材についても、グラスウール以外に、アルミ焼結板、セラミックス、石灰石等と開発されていますが、低音域の吸音特性が解決すればと今後期待できると考えています。
5 無響室における検収測定方法の変化
30年代の逆二乗特性成立の確認測定には、スピーカーからマイクの位置を変えるごとに重たいB&Kを手持ちして、息を殺しながら何十回も重たい扉を開閉しながら測ったものでした。効率も悪く、よく徹夜測定になり、測定者が座ったまま居眠りをしていたのを思い出します。(イビキの音がじゃまをした?)
40年代に入りますと、騒音計のマイクロホンを延長して計測者は室外で、マイクロホンを移動させる人間だけが室内に入る形になりました。測定はメジャーリングアンプ+フィルターで計測器の針を直読し、測定値を片対数グラフに直接記入していました。
50年前半からは、斜め上部の測定には、マイクの移動には移動式のワイヤー方式を取り入れました。測定は前項と同じです。
60年代に入りましてマイクの移動方法はワイヤーで同じですが、データの取り込みをリアルタイムアナライザをコンピュータで制御してデータをプロッターに記入する方式になりました。
これら測定方法の変遷(苦労の歴史)が、マイクロホン移動装置を生んだといえます。なお、その内容は、本誌No.1の「マイクロホン移動装置開発までの経緯」に詳しく述べています。
6 将来の無響室
今後必要とされるものとしては、
- A. 低音域用無響室
- B. 超高周波(20k~100kHz)用無響室
が考えられますが、低音域については、63Hz以下の遮断周波数(カットオフ)となると吸音楔の長さも1m以上必要で、室の規模も大きくなり、製作コストもアップするので、新たな吸音体の開発が今後の課題となります。
また、半分夢かと思いながら、航空機用などの超大型無響室も必要になる日が来るのではと考えています。
これからの21世紀に新しい発想のもと未来のために、無響室も時代のニーズに対応しながら発展していくことを信じて努力していきたいと思います。
最後になりましたが、日頃、お世話いただいている諸先生方、お得意先の皆様に心から感謝いたします。




